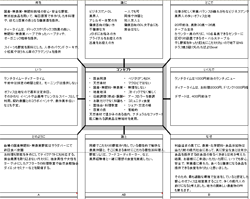2017年3月に武蔵小山に新しくオープンした、フレンチビストロ「MARTINIQUE(マルティニーク)」。
付き合いの長い3人が中心となって立ち上げた、お洒落で素敵なお店。
「友人同士で資金や資源を出し合い、同じ志を持って新しい事業を立ち上げる。」
「喜びも苦しみもシェアしながら、大きな目標に向かって一緒に頑張っていく。」
共同経営者として調理・接客などそれぞれの強みを活かすことで、魅力的なお店を経営されています。
とても素晴らしい!
「気心知れた仲間と一緒に飲食店を立ち上げたい」そんな夢をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
お互いの得意分野を活かし、良い店をより少ない労力で立ち上げられたり、苦楽を共にできるのもメリットですよね。
ですが、共同経営には注意しておかなければならない点があります。
『お客様が笑顔になって帰れる良い店を一緒につくろう!』そんな想いで考えうる最高の仲間とお店を立ち上げたとしても、必ず変化が訪れます。
2年後。3年後。
徐々にお互いの意見や主張に食い違いが生まれ、パワーバランスが崩れ、最後は喧嘩別れして崩壊してしまう・・・
これは飲食店経営に限ることではなく、どのビジネスでも起こりうること。
なぜ、共同経営が上手くいかなくなってしまうのでしょうか?
そこで今回は、飲食店の共同経営のメリット・デメリットと、よくあるトラブルとその回避方法を解説。
共同経営で成功を収める「フレンチビストロ マルティニーク」の現場でも実践される、
飲食店の共同経営で失敗しないための3カ条を、マルティニークの開業をサポートしたわたくし大森が解説します。
共同経営には「不平等」が必要、そう語るお三方の真意とは?
まずは共同経営のメリット・デメリットや、よくあるトラブルとその原因から紐解いていきましょう。
飲食店を共同経営する際の「メリットとデメリット」

「共同経営で飲食店を立ち上げたい」そういったご相談が少なくないのは共同経営には大きなメリットがあるから。
異なった専門知識を持つ人が一緒に経営することのメリット・デメリットを、切り分けて解説します。
【メリット】
- 役割分担ができ、得意分野で力を発揮できる
- 足りないスキルを補いあえる
- ひとりあたりの資金負担が減る
- 同じ目標を持った人同士で相談できる
【デメリット】
- 自分の思い通りにならないことがある
- 意思決定に時間がかかる
- 不公平感を感じる人が出てくる
いかがでしょうか?
複数の人間が関わることで、資金・責任・心理的負担などを分散できる一方、役割分担や人間関係により一層気を遣っておくことが必要です。
事業者として共にビジネスを始めることと、単に同じ職場で働くことは全く異なります。
では具体的なトラブル事例などを解説していきましょう。
共同経営で起きるトラブルとは?

「不公平感」「不信感」が生まれ、仲違いする
1番可能性が高いのはコレです。
共同経営はとにかくモメやすいのはなぜか。次項で詳しく説明します。
経営方針が合わなくなる
お店に真摯に向き合い、それぞれが成長した結果すべてがプラスに働くわけではありません。
例えばそれぞれが開業時には思いもつかなかったアイデアやメニューを考えつくかもしれません。
お互いにそのアイデア全てに賛同できれば良いのですが、場合によっては方針が合わないことも。
経営方針については、話し合いの場をこまめに設けるようにしましょう。
認識がズレている期間が長ければ長いほど、ズレは大きくなっていきます。
「このままでよい」という結論だから不要だった、のではなく、再確認できたことに意味があります。
辞めなければならない事情ができる
将来何が起こるか、だれにも予測することはできません。
もしかしたらメンバーのひとりが働けなくなる事情が生まれるかもしれません。
- 家族の介護など、面倒をみる必要が発生する
- 自身のケガ・病気
縁起でもないと怒られてしまいそうですが、そのリスクが発生する可能性がゼロではありません。
事業にかかわる人数が増え、それぞれが重要な役割を分担して担っているということは、
人に関するリスクもあるということです。
誰かが「欠けた場合にどうするのか」話し合い、事前に対策しておきましょう。
共同経営が「モメる」メカニズム

共同経営は「一つの事業に対し、二人以上の者がほぼ対等の立場で経営を行っていくこと、またその経営形態」を指します。
難しいのは、この「対等」という点。
共同経営を始めるにあたり開業資金を2人が同額ずつ出し合う、ということが良くあります。
同じ金額を出しているので、出資金という点では「対等」です。
ところが、事業運営で2人がまったく同じ仕事をする、ということはまずありません。
役割や責任範囲を決め、相互に補完しあう形でスタートする場合が多いですよね。
飲食店で言えば、一方がフロア担当、もう一方がキッチン担当といったように。
この時点では、負担や責任の「重さ」という点で「対等」と考え、「儲かったら半分ずつね」ということでお互い納得しています。
ところがしばらく運営していくと、必ずと言ってよいほど、どちらかが(あるいは両者が)「なにか不公平な気がする」と思うような事態が起きます。
(1)収益が「減って」も「増えて」も不満は出るもの

例えばお客様からクレームを受けた場合、
料理に髪の毛が入ってる!
スープが冷えてる!
⇒キッチンの責任
スタッフの態度が悪い!
グラスが割れて怪我をした!
⇒フロアの責任
どちらにも責任があることもあれば、明らかに一方がクレームの原因ということもあるでしょう。
ではどちらか一方が原因で起こった問題が口コミサイトなどで書き込まれ、集客が減ってお店の収益が激減したとします。
今まで通り「儲けは折半」で納得できますか?
アイツが悪いのに、なぜ俺の給料が減らされなければならないのか?
こういった不満は誰もが抱いてしまうものです。
しかもトラブルが起きた場合だけでなく、順調に利益が上がっている場合にも、「不満」が生じることがあります。
それはどういった状況でしょうか?
「このお店は料理の評判が良い。」となった場合。
キッチン担当は「俺のお蔭でこの店は繁盛している」という気持ちが強くなってきます。
それが積もると、「俺のお蔭で儲かっているのに、なぜ報酬が一緒なのか?」という不満に変わっていきます。
お笑いコンビの売れてる方が、「これでギャラは一緒か」と不満を漏らすのに少し似ていますね。(笑)
(2)不公平感が人間関係を悪化させる。
このように収益が「減って」も「増えて」も不満が出る可能性はあります。
「俺の方が頑張っているのに、報酬額が同じなのはおかしい。。」という不公平感が蓄積されていくと、どうなるでしょうか。
元々は仲が良かった共同経営者同士の人間関係に亀裂が入ります。
何でも「対等」に話し合いができたのに、どちらか一方の、あるいは両者の「不公平だ」という思いが強くなる。
こうなるともはや「対等」な関係とは言えません。
不満を表に出せずストレスが溜まったり、不満が爆発し口論になったり。
二人の人間関係は悪化の一途を辿り、お店の経営にも影を落とします。
「経営トップの雰囲気が悪い」「意見が対立し、運営方針がブレる」のは悪循環の始まりです。
現場にも悪いムードが広がり、働いているスタッフも楽しくないですし、お客さんにもそれが伝わり、お店の雰囲気を悪くします。
誰だって「雰囲気の悪いお店」になんて行きたくないですから、客足は遠のき売上も減少・・・。
もうこうなると、まともな経営はできません。
(3)最後は、利益の取り合い、責任のなすりつけ合い。
共同経営者同士がお互いに「不公平感」「不信感」を持つようになると、お店の利益について、それぞれが権利を主張し、奪い合いが始まります。
その逆で「損失」「トラブル」の責任は、お互いになすりつけ合うようになります。
その結末は、良くても「空中分解」。
最悪のケースは「倒産」「訴訟」にまで発展することもあります。
事実、当社には「共同経営が上手くいかなくなった」理由で、閉店や売却の相談に来られる方が多くいらっしゃいます。
その中には残念ながら訴訟問題にまで発展しているケースもありました。
そうなると、決定権者が複数いることで権利関係が複雑化し、閉店・売却すらスムーズに進みにくくなります。
共同経営を成功させるポイント

共同経営でスタートして、3年、5年、10年経っても、上手くいっているお店もあります。
お互いを信頼しあい、補完しあいながら、順調に業績を伸ばしているお店もあります。
「たまたま」ではなく、共同経営を上手く成立させるためには、どんなポイントがあるでしょうか。
(1)業務領域・責任範囲・分配割合を明確にし、ルール化しておく
それぞれの経営者が、どの仕事を行ない、何に対してどこまでの責任を負うのか、をあらかじめ設定しておきます。
業務領域・責任範囲に応じた分配割合(報酬体系)を決めておくことも重要です。
説明したように「不公平感」は店を崩壊させる一因です。設定したルールはきちんと書面化までしておきましょう。
(2)意見が分かれた時の意思決定方法をあらかじめ決めておく
経営者も人間ですから、当然、お互いに意見が分かれることがあります。
どちらの意見にもそれぞれ正論があり、微妙な判断となることも。
しかし複数の経営者が互いに違うことを言っていると、現場が大混乱してしまいます。
事業を上手く進めていくためには、経営方針・経営理念・ビジョンは常に一致させておく必要があります。
経営者同士で意見が分かれた場合の「最終的な意思決定方法」は前もって定めておくべきです。
個人事業でのオススメは、名義人となっている方を最終意思決定権者とすること。
物件契約・融資申請・営業許可申請等の名義人(契約者)となっている人がいるはずです。
法的にも、実務上も、重い責任を負っています。
法人としてスタートする場合も同様。
代表者(代表取締役)をひとり選出する場合には代表者が、複数代表とする場合には出資割合や業務負担割合に応じて、という考え方になるでしょう。
代表者が3名の場合には多数決で決めるという選択肢も考えられます。
(3)相互に、尊敬し、信頼し合える関係作り
同じ分野の仕事を担っていると、どうしてもその仕事の「量」や「質」の点で、優劣が生じてしまいます。
それぞれに得意分野(専門領域)を持っておくのがベスト。
お互いに「この分野については、俺よりアイツの方が詳しい」「この分野は彼の判断に任せておけば大丈夫」という信頼関係が重要です。
お互いに「なくてはならない存在」としてパワーバランスが取りやすくなります。
武蔵小山「MARTINIQUE(マルティニーク)」の場合

武蔵小山に新しくオープンしたフレンチビストロ「MARTINIQUE(マルティニーク)」は、お互いに信頼し合う佐々木さん・宮川さん・中橋さんの3人が「共同経営者」として立ち上げたお店。
経営方針や将来のビジョンについては、3人で十分に協議を重ねました。
責任範囲や役割を明確化するため、事業開始前に法人(会社)を設立。

もっともお客様との距離が近く、対外的に動くことが多いフロア責任者(支配人兼シニアソムリエ)の佐々木さんが代表に就任し、経営全般の総責任者という役割を担っています。
キッチンに関しては、料理長は宮川さん・副料理長は中橋さんとしました。
都内有名フレンチレストランでの調理経験・実績を多く積み、店名の由来となったフランス・マルティニーク島でそのエッセンスを吸収した宮川さんを料理長に。
宮川さんとは異なる料理ジャンル(スペイン料理等)での経験・実績を持つ中橋さんを副料理長に。
お互いの強みを発揮しながら、素晴らしい創作料理の数々を生み出しています。
提供するメニューについて意見が割れた場合、最終的な決定権は調理長である宮川さんにあると、3人で決めました。
「誰が」最終決定権をもっているか明確だから、スムーズ
出店場所・店名・店舗デザイン・メニュー構成・価格設定など、重要な経営判断については3人の話し合いで決めることが原則。
そうしながらも、意見が分かれた時に、どの分野について、誰が最終決定権を持つかを明確にしています。
「任せるべきものは信頼して任せる」という権限移譲(権限分化)が適切に行われていることで、「MARTINIQUE」はスムーズな開業を実現することができました。
共同経営を目指している方、実際に来店してお三方をご覧になってください。
論より証拠です。
飲食店の共同経営をお考えの方は、ぜひマルティニークに足をお運びください。
3人の会話やコミュニケーションの取り方、店舗での動き方など見ていると、佐々木さん宮川さん中橋さんがそれぞれお互いの能力を認め合い、尊敬し信頼し合っていることがよく分かります。
(たまには喧嘩しているかも知れませんが。。笑)
お三方であれば、これからも力を合わせ、上手くバランスを取りながら共同経営のリスクを克服し、「三本の矢」のように簡単には折れない「強いお店」を作っていかれるに違いないと思っています。 大森
大森
| 店名 | MARTINIQUE(マルティニーク)閉店 |
| TEL | 03-6426-9159 |
| 住所 | 東京都品川区荏原3-3-25 2F
(武蔵小山駅駅より徒歩4分) |
| 定休日 | 月曜日 |
LINEで新着情報を配信中!
![]()
飲食店開業・経営に役立つ情報やセミナーの特別無料ご招待を月2回ほどお届けします。
お役立ちツールの無料ダウンロード
■開業前にお店のコンセプトをしっかり考えるなら
その他の、飲食店で使える無料開業ツールの一覧はこちら。
資金調達・物件探し・店舗内装デザイン・人材採用・集客・助成金など!
26のツールが無料でダウンロードできるお役立ちページです。
無料セミナーのご案内

物件探しの極意
物件探しの「目からウロコ」の情報をお伝えします。
《セミナー内容》
・1等立地は儲かるのか
・良い物件の判断基準は?
・物件に出会いにくい人の特徴とは?
・条件交渉は可能? しやすい部分は?
会場: 東京
「事業計画」「資金調達」の極意
満額融資に必要な、机上ではない実践的な融資ノウハウをお伝え。
《セミナー内容》
・親から借りたお金は自己資金としてみなされる?
・売上予測は○パターン用意しておくといいっていうのは本当?
・融資実行までの流れは? どのぐらいの時間がかかるの?
・申請書類はしっかり書いたけど、審査が通らない理由とは?
・一発退場! 融資面接時のNGワードとは?
会場: 東京